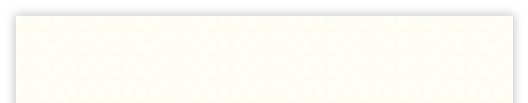三つ具足(みつぐそく)は、仏壇に欠かせない基本的な仏具の一式で、日々の供養の中心的役割を果たします。
三つ具足とは
「三つ具足」とは、花立、香炉、燭台の三つをそろえた仏具のセットを指します。 花立には供花を、香炉にはお香を、燭台にはロウソクを立て、香・花・灯明の三つを仏に備える形で礼拝します。 これらは仏教で「三大供養」とされ、仏に対して感謝や祈りの心を表すものです。
三つの道具の意味
それぞれの仏具には象徴的な意味が込められています。
・花立:仏の慈悲を象徴し、生花を供える事で生命や清らかさを表現します。
・香炉:お香を焚く身を清め、心を整えるとされています。
・燭台:灯明をともす事で仏の智慧(ちえ)の光を示し、迷いや闇を照らすとされています。
これらの三つが揃う事で、仏壇が「完全な供養の場」として整うのです。
配置と使い方
三つ具足を仏壇に飾る際は、仏様に向かって左に花立、中央に香炉、右に燭台をおくのが基本です。 左右は仏様側からみて決まるため、参拝する側から見ると左右が逆になります。 お供えや点灯の際は、故人やご本尊に敬意を払いながら丁寧に扱う事が大切です。
歴史と宗派による違い
三つ具足の概念は、仏教が日本に伝来したころから存在し、室町時代から江戸時代にかけて広まりました。 一方で、宗派によっては四つ具足や五具足が用いられることがあります。 三つ具足は省略形で、五具足は左右対称になるように花立と燭台を2つずつそろえた正式方とされています。
現代の三つ具足の選び方
現代では、仏壇のサイズや住宅事情に合わせ、陶器・真鍮(しんちゅう)・モダンデザインなど様々な素材、形状の三つ具足があります。 大きめの仏壇では五具足が選ばれる場合もありますが、家庭用としては三つ具足が一般的です。 どの素材であっても、供養の心を込めて整える事が何より大切です。
まとめ
三つ具足は、仏壇を構成する基本であり、仏様への感謝や祈りを形にした供養の道具です。 花・香・灯の三つを供える事で、日常の中で心を静め、故人や仏に対する敬意を新たにする大切な時間を作り出します。
イソラメモリアル株式会社
福岡市博多区下呉服町8-1
0120-04-3096