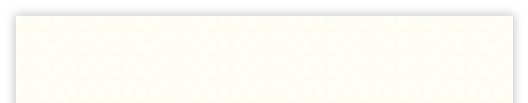守り刀とは、日本の葬儀でよく見られる儀式用の短刀または模造刀で、亡くなった方の胸元や枕元に置く風習です。 古くから日本の葬送儀礼に伝わるもので、その起源や意味、使い方には深い歴史と地域ごとの特色があります。 守り刀の根本には「大切な故人を災いや邪悪な物から守り、安らかな旅立ちを祈る」という思いが込められています。
守り刀の歴史
守り刀の歴史は、武士の時代や遥か古代の埋葬事情にまでさかのぼると言われています。 弥生時代にはすでに、刀剣に霊力があると信じられ、武士だけでなく多くの人々が魔除けや厄除けとして身に付けていました。 特に武士階級では、日常的に刀を所持し、夜も枕元に刀を置く「枕刀」という習慣が広く存在したほか、亡くなった際には「武士の魂を象徴する脇差や短刀を故人の傍に添える儀式が行われてきました。 この風習がやがて町人や庶民にも広がり、地域の葬儀に定着しています。
守り刀の背景
守り刀の背景には宗教的背景も色濃く、仏教では「中陰」と呼ばれる四十九日の間、故人が極楽浄土に無事に渡れるよう「追善供養」の一環として用いられています。 神道では、死の「穢れ」を祓う為に守り刀が添えられてある事が多く、これは死者の魂が穢れになり生者に影響しないように「祓い」の役割とも重なります。
守り刀の意味
守り刀の意味としては魔除けや厄除けだけにとどまりません。 葬儀では猫除けとしての役割もありました。 昔は猫が亡骸に近づくことを嫌った為、猫が光物を避ける修正を利用して、刀を置いたとも言われています。 また、花嫁が嫁入りの際に守り刀を持たせる習慣や、子供の成長を願って短刀が贈られるなど、家族や子孫を思う願いが守り刀に込められてきました。
現代における守り刀
現代においては、模造刀製の短刀が主流です。 銃刀法により15cm以上の刀剣は許可なく所持できないため、ほとんどが短く安全な仕様になっています。 火葬時、木製であれば棺と共に焼却することも出来ま、金属製は火葬場で外す必要があり、必ず事前に相談する事が大切です。 宗派や地域によっては守り刀を使わない事もありますので、担当の寺院や葬儀社へ確認するのが安心です。
まとめ
現代では葬儀の儀礼的な意味が強調されがちですが、その背景にある家族への思いや故人の旅立ちへの祈りは、昔も今も変わらぬものです。 守り刀は形や材質を変えても、「大切な人たちを守る」という優しさと敬意の象徴であり続けています。
直葬 家族葬 一般葬 一日葬
各宗派、各葬儀形式に対応させていただきます。
~どこまでも、家族に寄り添うお葬式~
イソラメモリアル株式会社
福岡市博多区下呉服町8-1
0120-04-3096