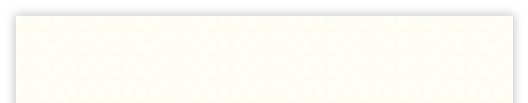釘打ちとは?
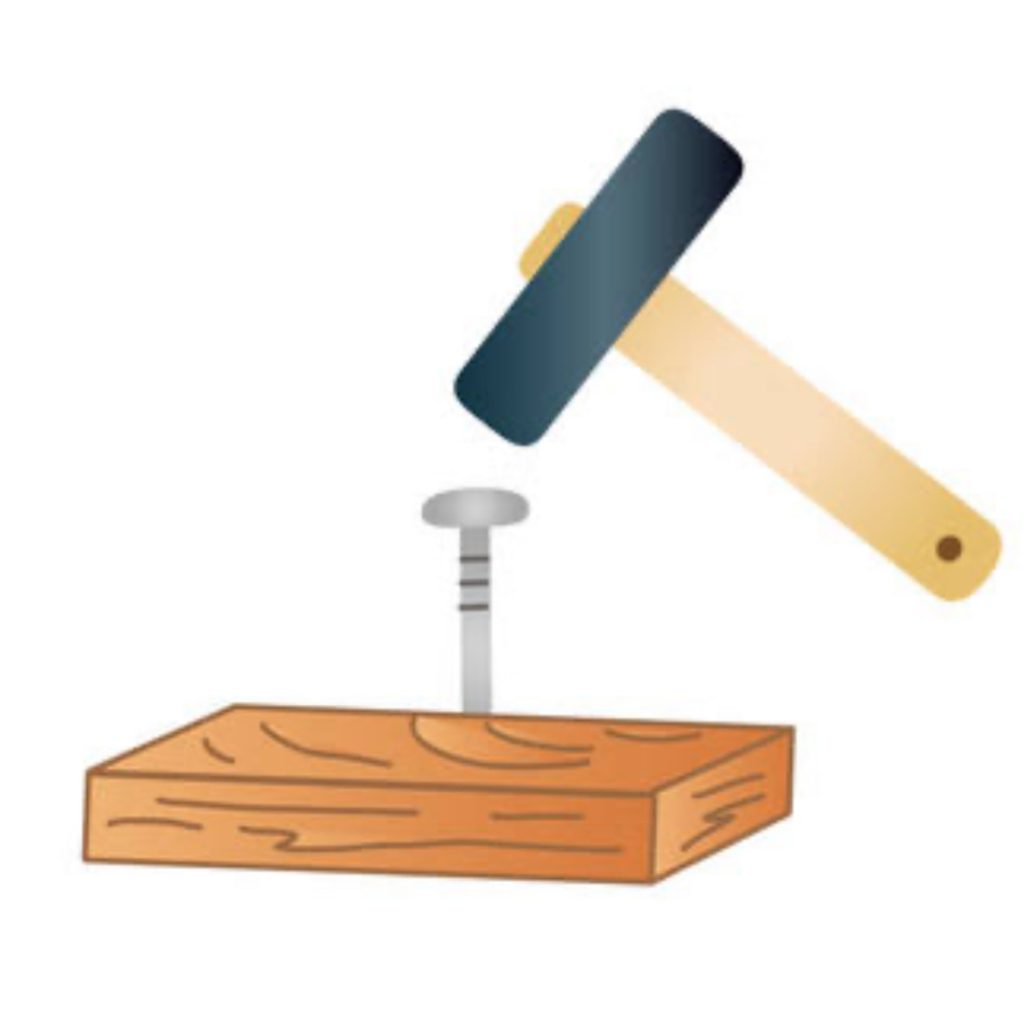
葬儀における「釘打ち」は、棺の蓋を釘で打ち付ける儀式で、出棺の際に行われます。 この儀式には、宗教的・実用的な意味が込められており、地域や宗派によってその形式や、意義が異なります。
釘打ちの主な目的
1.故人との別れを受け入れる為
釘を打つ行為は、遺族が故人との別れを受け入れ、心の区切りをつけるための象徴的な行動です。
2.穢れを封じるため
神道では「死」を穢れとして捉え、棺をしっかりと閉じる事で穢れや霊力が外に漏れないようにする意味があります。
3.運搬中の安全確保
土葬が一般的だった時代には、棺が運搬中に開かないように釘打ちが行われていました。 特に湿気で木材が反りやすい無垢材の棺では重要な役割を果たしました。
釘打ちの流れと道具
①手順
・喪主から血縁の濃い順に、棺の頭側から石や金づちで釘を軽く打ちます。
・その後、葬儀社スタッフが最後まで釘を固定します。
②道具
・昔は三途の川の石に例えられる小石が使われていましたが、現在では金づちが一般的です。
現代における変化
火葬の普及:
火葬が主流となった現代では、棺の構造が進化し、蓋がしっかり閉まるため釘打ち自体は不要になりました。 ただし、儀式として形式的に行う場合もあります。
省略されるケース:
遺族の意向や宗教観によっては、「個人への配慮」から釘打ちを省略されることも増えています。
まとめ
「釘打ち」は単なる実用的な行為ではなく、故人への思いや別れを象徴する大切な儀式です。 現代ではその形式や必要性が変化していますが、それでも多くの場合、この儀式には遺族の心情を整理する役割が残されているのかも知れません。