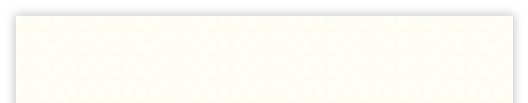六文銭は、日本の歴史や葬儀文化に深くかかわる象徴的な存在であり、「三途の川の渡し賃」としても広く知られています。
六文銭の歴史と価値
六文銭とは、江戸時代以前に使われていた一文銭(最小単位の貨幣)を6枚集めた物を指します。 奈良時代から明治初期まで用いられた通貨で、旅の通行料やお賽銭、特に死者の棺に納める葬送費用として用いられました。 現代の貨幣価値に換算すると、六文銭は概ね180円~300円前後と考えられていますが、当時の庶民にとっては決して安い金額ではありませんでした。
六文銭と葬儀文化
仏式の葬儀では、故人の棺に六文銭を納める事が定番の習わしです。 これは「三途の川」を渡るための渡し賃として必要だとされ、六文銭を持たせることで故人が浄土までの道のりで困らないようにとの願いが込められています。 この風習は、仏教の三途の川の教えに基づき、死者が来世へ円滑に渡れるよう送り出す日本独特の死生観から生まれました。 地域によってはさらに多くの銭を納める事もあり、あの世でも経済的不安がないよう願う意味があります。
真田家の家紋と六文銭
六文銭は、戦国武将・真田家の家紋「六連銭(むつれんせん)」としても有名です。 勇猛果敢な真田幸村が自軍の覚悟を示したシンボルとされ、時代劇やドラマにも度々登場します。 今日では歴史祭りや神社、寺院でお守りや縁起物として六文銭のレプリカが用いられることもあります。
六文銭を棺に入れる際の注意点
現代の葬儀では、実際の硬貨紙製やプラスチック製の六文銭のレプリカを用いるケースが多く、宗派や地域の習慣に留意して納棺することが大切です。
六文銭は古銭であるという事以上に死者への祈りや歴史、家紋、文化の象徴です。 日本の伝統や思いやりが込められた六文銭の風習は、今後も大切に受け継がれていく事でしょう。
直葬 家族葬 一般葬 一日葬
各宗派、各葬儀形式に対応させていただきます。
~どこまでも、家族に寄り添うお葬式~
イソラメモリアル株式会社
福岡市博多区下呉服町8-1
0120-04-3096
福岡市 中央区 博多区 東区 南区 西区 早良区 城南区 糟屋郡