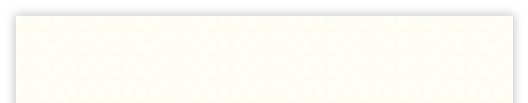近年、終活は高齢者だけでなく、20代・30代の若い世代にも広がっています。 その一方で、「デス活」という新しいムーブメントも注目を集めています。 若者終活の流行とデス活の特徴、両者の違い、そして社会的な意味について詳しくまとめます。
若者の間で終活・デス活が広がる理由
SNSやネットを通じて終活・デス活の情報が手軽に得られ、「死」へのタブー意識が薄れつつあります。 突然の死や社会的な不安が増え、「今をどう生きるか」を考えるきっかけとなっています。 また、終活は「備え」として、デス活は「自分らしい生き方・死に方」を探るための活動として、若者に受け入れられています。
デス活とは? その特徴と広がり
デス活は”死”(Death) と”活動”を組み合わせた造語で、お茶やお菓子を楽しみながら、死についてカジュアルに語り合う活動です。 欧州発の「デスカフェ」を参考に、日本では2018年から心理師の吉田英史氏らが展開。 カフェや寺院、ショッピングモールなどで月1回程度開催されています。 20~30代を中心に、死を「ポップに」「前向きに」捉えるイベントやフェスも盛況。 2025年の「Deathフェス」には10代から90代まで幅広い世代が参加し、入棺体験やトークセッションなど多様なプログラムが実施されました。 デス活では否定をしない、信条を押し付けないといったルールが設けられており、誰もが安心して語れる場作りが重視されています。
終活・デス活がもたらすもの
死をタブー視せず、オープンに語る事で「今をどう生きるか」を考えるきっかけになり、悲嘆や孤独の緩和、家族や友人との関係の見直し、人生の優先順位の明確化に繋がります。 また、実務的な準備(終活)と、内面を見つめ直す対話(デス活)が補完し合い、より豊かな人生設計が望めるでしょう。
まとめ
若者の終活は「死後の備え」から「今をどう生きるか」への意識転換が進み、デス活はその象徴的な活動となっています。 終活・デス活は、世代や立場を越えて、これからの日本社会に不可欠な新しいライフスタイルとして定着しつつあります。